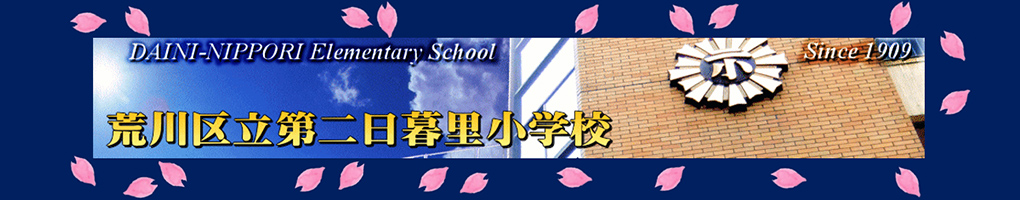本校の特色
ICT機器の活用
21世紀型スキルの習得をめざして、1人1台のタブレットPC
本校は荒川区教育委員会・タブレットPC導入モデル校として、全児童に1人1台のタブレットPCが配布され、平成25年9月からタブレットPCを使った授業を行っています。すべてをタブレットPCで学ぶのではなく、普段づかいの学習ツールの一つとしてのタブレットPCの活用を心がけています。
【導入時の様子】

興味津々

教えてくれます

教えてくれます
タブレットの良さを普段の授業の中にどのように取り入れることができるのか、試行錯誤の繰り返しですが、電子黒板やデジタル教科書と連動させて、さまざまな授業が工夫され実践されるようになってきました。
【算数の学習で(高学年)】

タブレットPCでまとめます
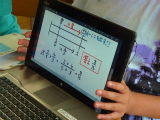
タブレットを見せ合います

画面を電子黒板に映し出して発表
算数だけでなく、生活科や理科の観察記録、体育のフォームを撮影して改善するなど、多くの教科で活用しています。特に写真や発表の場面でのコミュニケーションツールとして使う場面が多く、展覧会では、
5・6年生がタブレットをもって、参観者に説明する「展覧会ガイド」を行いました。
【1年生の様子】
1人1台ですから、もちろん1年生も使います。

しっかりと覚えます

文字を書いたり、

みることができます
タブレットPCは、教室だけでなく、体育館や校庭、そして、校外学習でも活躍します。

行ってきました


自由に写真を撮ります
他にも都道府検定や持久走記録大会でのラップタイムの記録、また、3年生からのローマ字の学習にも効果を発揮しています。これからもさまざまなアイデアを形にして、よりよい授業に役立たせていきたいと考えています。
ICT機器の活用・プログラミング教育
平成28年度
- 文部科学省事業の中で、プログラミング教育を行いました。
- 第3学年、総合的な学習の時間(2時間×3回)
- LEGO Education様とその代理店(株)ナリカ様に協力をお願いし、10台のLEGO「マインドストームEVⅢ」をお借りしました。

参考に、アンプラグドな
導入

同じく、命令のブロック
をつなげていく

転送し、スタート!

戻ってみんなで考える


動いてくれるだろうか
平成27年度
- 荒川区教育研究指定校として算数科の研究発表を行った際、全学級タブレットPCを活用した授業を公開しました。
- 3年生以上では、算数科の問題解決型授業の自力解決、検討場面で自分考えタブレットに表現し、共有します。

式でかいてみる。容易に
修正できるのも利点
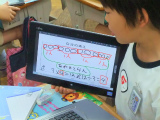
友達に考えを分かりやすく伝える

電子黒板に映して考えを
全体に説明する
- 低学年では、操作活動や、ノーに書いた自分の考えをタブレットで写真に撮り、電子黒板で共有します。

タブレットPCで撮影する


低学年でも説明が容易になる
平成26年度~平成28年度
- 荒川区が、総務省「先導的教育システム実証事業」、文部科学省「先導的な教育体制構築事業」による実証地域に指定され、本校の他3校が具体的な取り組みを進めました。
- SIMカード付きのタブレットPC40台と電子黒板2台が貸与されました。
- 総務省事業では、主にクラウドシステムを活用した学習コンテンツが提供され、学校内での活用とともに、家庭に持ち帰って活用する方法等について検証しました。
- 文部科学省事業として、ICT機器を活用した授業検証、独自の学力調査等が検証されました。
平成25年度
- 荒川区タブレットPC先行導入校として、タブレットPCが一人1台配備されました。
鮭の稚魚を育てる「鮭の里親事業」
平成24年度から、荒川区の交流事業として、尾久宮前小と一緒に、
山形県鮭川村、および鮭川小学校と交流しています。


10月・2月 【木の子の日給食】
「木の子」は、鮭川村の特産物です。鮭川村からいただいた「木の子」を使って給食を作り、3校がウェブカメラで同時中継しながら、学校紹介をして給食をいただきます。




12月【鮭川小の友達が鮭の卵を持ってきてくれます】


3月 代表児童が鮭川村を訪問して、稚魚を放流!


【鮭川村訪問の様子はこちらからご覧ください】
その他の特色ある教育活動
夢をもって かがやけ 二日っ子

二日小マーチングバンド
運動会では、3年生の全児童がマーチングフラッグで参加
4年生以上の全児童が学校や地域の行事で日ごろの練習の成果を披露




学校図書館の活用 読み聞かせ


PTAもちつき
保護者・地域の方々のご協力をいただきながら体験する日本の伝統行事


オリンピック・パラリンピック教育推進校
2020年の東京大会の開催に当たり、様々なオリンピック・パラリンピック教育やコオーディネーショントレーニングを実践



持久走記録会
目標を達成するために努力を続けるたくましい心と強い体づくり


ににちフェスタ
1年生や保護者の方々を招き、2年生以上の児童が企画・運営するおまつり